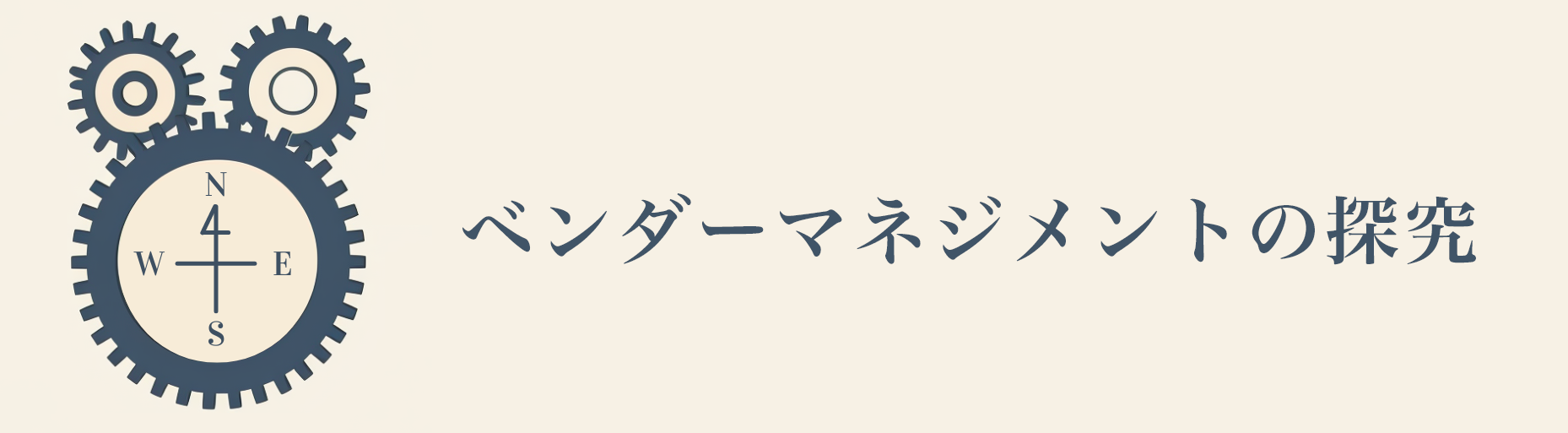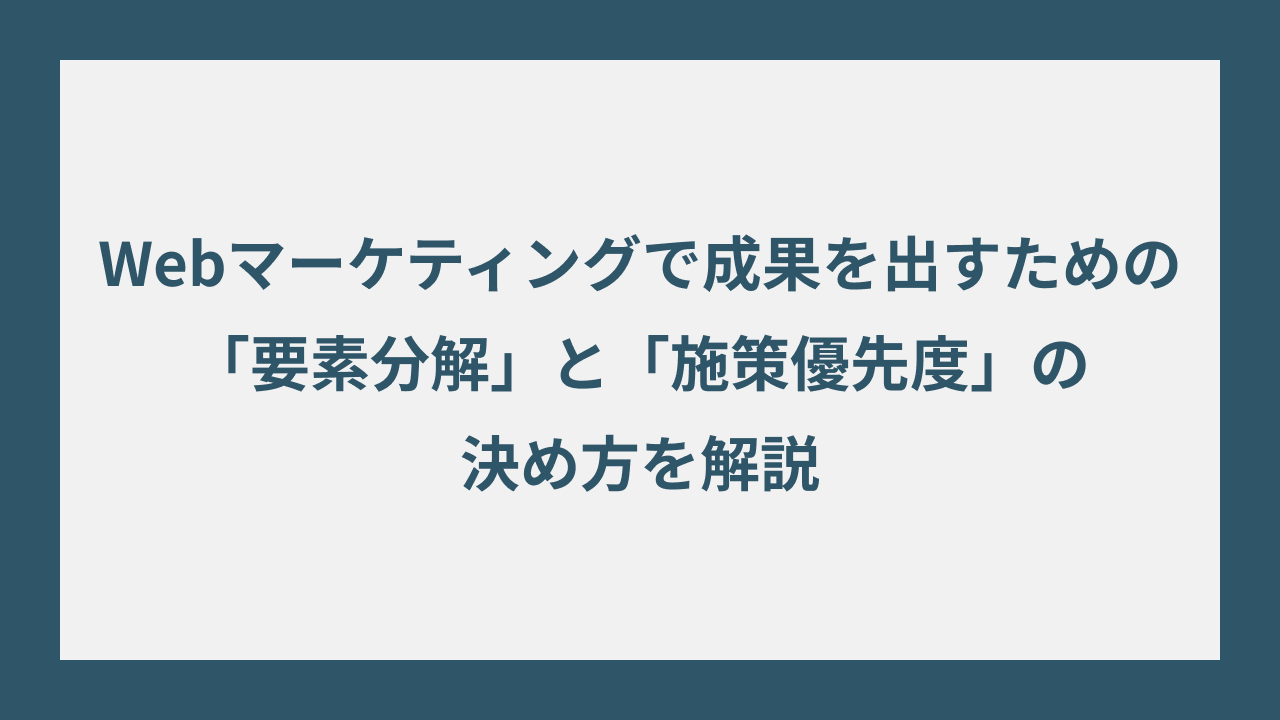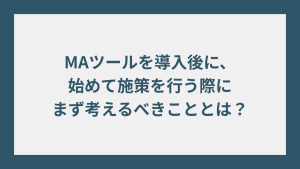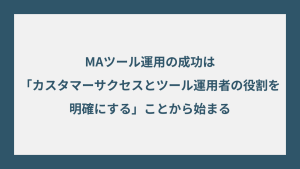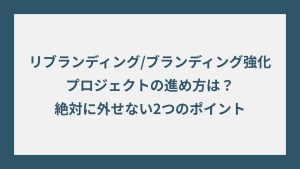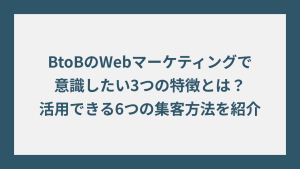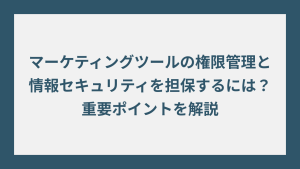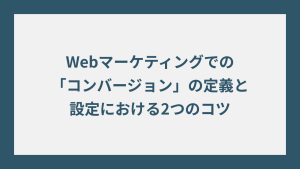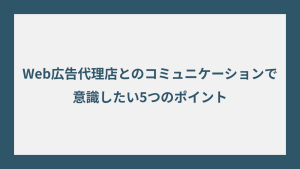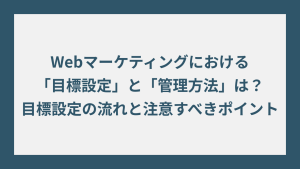この記事では、事業でWebマーケティングを活用していく上で、限られたリソースで効果的な施策を積み重ねて大きな成果につなげるための要素分解と施策優先度の決め方について解説します。
成果は何かを考える
まずは、みなさんが運営している事業やサービスにとっての「成果」は何なのかを明確にする必要があります。成果ということばには、文字通り「成し遂げて得る結果」という意味があり、みなさんが事業やサービスを通じて得たい結果とは果たして何なのかを考えてみると良いでしょう。
たとえば、次のものなどが挙げられます。
- 売上
- 利益
- 購入数
- サブスクリプション登録数
- フォーム申し込み数
- 電話問い合わせ数
- メルマガ登録数
- 会員登録数
- 資料請求ダウンロード数
- コメント、口コミ投稿数
- SNSアカウントのフォロー(友だち追加、チャンネル登録など)数
- SNSでのシェア、投稿数
- 動画コンテンツの閲覧数
当たり前のことですが、事業やサービスによって得たい結果(成果)は異なります。そして、何を目的に置くか、担当領域はどこか、どんなフェーズにあるかなどによっても非常にさまざまな成果の捉え方が考えられるのです。
成果は要素ごとに分解できる
事業やサービスで最終的に追うべき成果が明確になってきたら、その成果が何によって成り立っているのか、要素ごとに分解してみましょう。ここでいう要素は、「指標」とも表現されます。また、「成果を分解する」という意味だと、KGI、KPIツリー(重要指標同士の関係性を枝葉構造で整理したもの)なども同様の考え方です。
ここでは、仮にECサイトで化粧品の単品リピート通販をするA社があるとして、最終的な成果を要素ごとに分解する具体例を紹介します。
A社は月に1,000万円の売上があり、この「売上」を最終的な成果として追っています。そしてこの売上は、「新規顧客」からの売上と「既存顧客」からの売上に分解されます。
- 全体の売上(1,000万円)=新規顧客の売上(100万円)+既存顧客の売上(900万円)
新規顧客の売上は、ECサイトに訪れる新規訪問者数と初回購入率、そして購入単価の掛け算からなります。
- 新規顧客の売上(100万円)=新規訪問者数(10,000人)×購入率(1.0%)×購入単価(1万円)
さらに、新規訪問者数は自然検索、Web広告、SNSオーガニック流入、SNS広告、その他に分解できます。
- 新規訪問者数(10,000人)=自然検索(1,000人)+Web広告(4,000人)+SNSオーガニック流入(500人)+SNS広告(4,000人)+その他(500人)
既存顧客の売上は、定期購入者数と購入単価、そして継続率の掛け算からなります。
- 既存顧客の売上(900万円)=定期購入者数(900人)×購入単価(1万円)×継続率(99%)
このようにして成果の要素分解を進めていくと、何がどの程度、売上という最終的な成果に対してつながっているのか、関係性や貢献度合いが見えてきます。たとえば、次のようなことが挙げられます。
- 売上のほとんど大部分は既存顧客から上がっていること
- とはいえ新規顧客を増やさないことには売上も上がっていかないこと
- 新規顧客のほとんどはWeb広告とSNS広告の流入に依存していること
要素分解はどんどん細かくしていくことができるため、自分の担当する領域について深掘りをして解像度高く把握していることが非常に重要です。
成果はさまざまな要素の足し合わせや掛け合わせで成り立っていますが、その要素が多ければ多いほど改善する余地となり得ます。そのため、一つひとつの小さな改善でも積み重ねれば、指数関数的に大きな成果につながっていくように、要素が多いことが非常に大きな意味を持ちます。
たとえば、成果を5要素で捉えている場合と、10要素で捉えている場合とで、それぞれの要素ごとに10%の改善を積み重ねた際の差分を単純計算すると(成果=全要素ごとの掛け算と仮定)、次のようになります。
- 5要素:161%の改善
- 10要素:259%の改善
つまり、単に成果を5個の要素で分解したか10個の要素で分解したかによって、1.6倍の差が生まれたということになるのです。
1.6倍というと小さく感じるかもしれません。しかし、事業は複雑でさまざまな要素を含むため、数百以上の要素から成り立つなんてこともあり得ます。そうすると、事業に対する解像度の高さがどれだけ最終的な成果に及ぼす影響が大きいか想像いただけるのではないでしょうか?
みなさんの事業やサービスでもどんな要素が考えられるか、鳥の目虫の目魚の目で見てみて、ぜひ探求してみてください。
成果につながりやすい施策優先度の決め方
成果を改善するための施策を考える際には、成果を分解した要素を大まかに次の3つに分別します。
- ①軽い変数(小さなリソース投下で変えられるもの)
- ②重い変数(大きなリソース投下で変えられるもの)
- ③ほぼ定数(何をしてもほとんど変えられないもの)
※リソースとは時間、お金、労力などを指します
基本的には、まずは①に対する施策を洗い出し優先度高く実施して、リソースが許す限り②に対する施策検討と実施を進めていくと、限られたリソースの中でできるだけ大きな成果につながります。
「③ほぼ定数」については、意図的に改善対象から除外することが何より重要だといえるでしょう。筆者自身、これまでさまざまなWebマーケティングの現場で施策案の洗い出しや実施をしてきましたが、ありとあらゆる1から100まですべてを完遂できる潤沢なリソースがあるということは絶対になく、常に限られたリソースと睨めっこしながら、その中で最大限の成果を得るためにはどうしたら良いのか模索してきました。
その過程において、「まず何をしないか」「何には手をつけないか」を明確にすることが第一歩目として非常に重要だと感じています。「③ほぼ定数」で”ほぼ”としているのは、1時間、1日、1週間、1ヶ月という尺度ではなかなか変えられないものではあるけれど、どんな要素も時間経過と共に変わりゆくためです。
また、成果を要素ごとに分解していくと、おおまかに「量に関するもの」と「質に関するもの」とに分類されます。「量に関するもの」とは、例えばサイトの閲覧数や広告の表示回数、動画の閲覧数などがあります。一方で、「質に関するもの」とは、たとえば問合せ率や申し込み率、購入率などです。
このときに、「量に関するもの」から優先して改善を図ることをおすすめします。というのも、「質に関するもの」の改善は、量があるからこそ影響が強まり(逆に量が小さい場合は改善しても影響は小さい)、量が担保されている状態の方が改善しやすい(質を改善するための情報が十分に集めやすい)という特性があるからです。
まとめ
Webマーケティングで成果を出すための要素分解と施策優先度の決め方について、具体例を交えて解説しました。
事業の成果を何に置くか、そしてその成果を分解した各要素(指標)に対してどのように施策優先度を決めて実際の施策を積み上げて総和としての改善をするかが非常に重要です。
私たち株式会社Geneは、デジタルベンダーマネジメントという領域に強みをもち、総合的な観点から事業会社のより良いベンダー選定や事業推進の一助となれるよう、これまで数多くの現場で尽力してきました。Webマーケティングで成果を出すための要素分解と施策優先度の決め方にお悩みの場合は、ぜひお気軽にご相談ください。