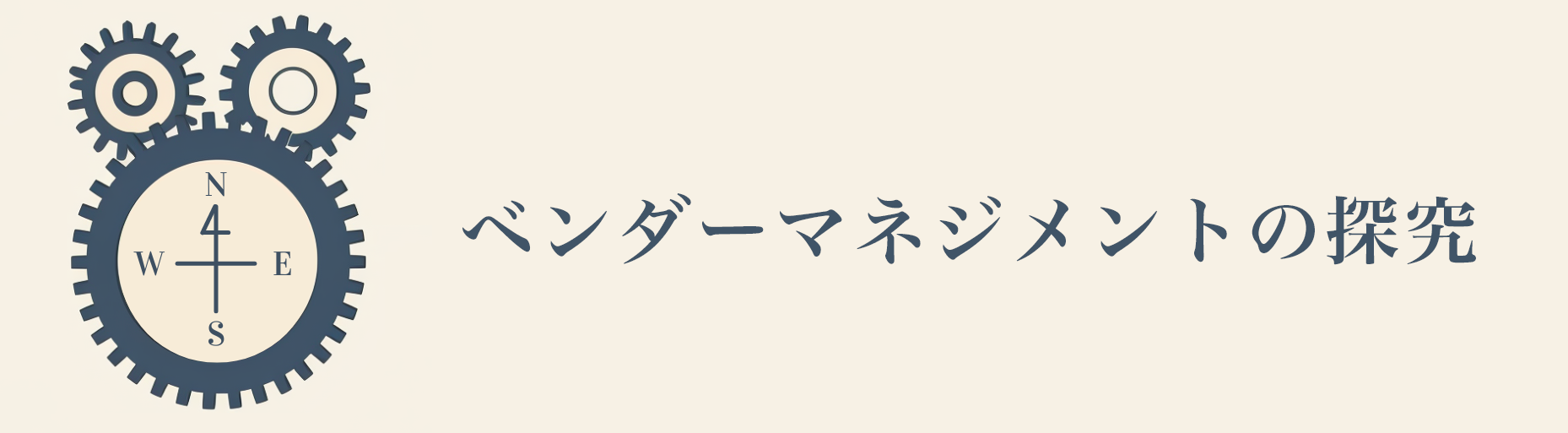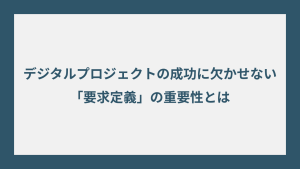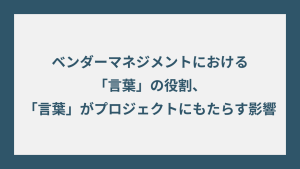デジタルトランスフォーメーション(DX)が加速する中、多くの企業がデジタルベンダーとの協業を進めています。プロジェクトの成功を左右するベンダー選定において、他社の成功事例を鵜呑みにすることで失敗するリスクがあります。筆者自身、多くの企業のDXプロジェクトに携わる中で、この点に悩む担当者の方々を数多く見てきました。
ベンダー選定はプロジェクトの成功を左右する重要なプロセスです。事業者は、自社の実現したいものや課題を解決するために、どのようなベンダーとパートナーシップを組んでいくべきかを見極める必要があります。この過程においてベンダーが過去のプロジェクトの成功事例を提示することが多いのですが、そこには落とし穴が潜んでいます。
ベンダー選定の難しさは、ベンダーが自分たちで行った過去のプロジェクトの「成功事例」の取り扱いにあります。ベンダーマネジメントに限らず、ビジネス全般において「できること、実績があること」に対してお金が支払われます。しかし、デジタルやシステム領域を筆頭に、最終的に出来上がるまでどのようなモノになるかわからないビジネスにおいては、この「できること、実績があること」の証明や再現性を持たせることが非常に難しいのです。
事例と成功は切り分けて考えるべきですが、担当者の方々は各ベンダーから上がってくる細かい仕様や開発要件を見ても、それだけではわからないことが少なくありません。さらに、確認をする時間がないこともあるでしょう。提案するベンダー側もその担当者のリテラシーや忙しさを知っているので、要件は詰めつつも、似たようなプロジェクトでの動きを引用しながら説明をしたり、そのプロジェクトと近しい成果を掲げたりします。
この動き自体は何も悪いことではなく、説明コストを省き、双方がプロジェクトの共通認識を保つために叩き台としては必要な取り組みです。しかし、成功事例を無理やりはめ込んでしまっているように見えるパターンもあります。ベンダーに悪意があるわけではなく、イメージを持ってもらいやすい説明をするためであったり、上申をしやすくするためであったりします。いわば、事業者の担当者さんへ寄り添うための行為ですが、叩き台の出発点がズレてしまうとプロジェクトが失敗してしまうため注意が必要です。
筆者は、担当者の方々が抱えるこうした悩みや課題に寄り添い、一緒に解決策を探っていきたいと考えています。他社の成功事例に惑わされることなく、自社のビジネスとの適合性を見極め、ベンダー選定を行うことが重要です。ここでは、その具体的な方法について解説します。
成功事例をフィットさせるための3つの視点
他社の成功事例が自社にフィットしているかを見極めるために、次の3つの視点を確認することが重要です。
- 文化/商習慣の違い
- ビジネスモデルの違い
- ターゲット(お客様)の違い
1. 文化/商習慣の違い
先進的な事例であっても、国独自の商習慣・ルールや文化が異なると、それをそのまま転用することは難しいです。
日本においては、欧米での先進的な事例や最近では中国での事例などを鵜呑みにしがちですが、デジタルやシステムの手間にそもそも国独自の商習慣・ルールや文化の大きな違いがあります。日本で同等のことをやっても、誰も求めていなかったり、誰も使いこなせなかったりすることが起きてしまうので注意が必要です。
ただし、欧米での先進的な事例や変化は、半年~2年のラグで日本にも導入される動きもあります。そのため、世界の大きな流れの変化としてウォッチしておくことをおすすめします。グローバルな視点を持ち、自社の文化や商習慣とどう折り合いをつけていくかを考えることが重要です。
2.ビジネスモデルの違い
日本国内での事例においても、それぞれのビジネス上のKPIや購入動機/周期がバラバラであるため、自社の目指す体験に合わせてチューニングが必要です。
たとえば、デジタル業界でバズワード化している「OMO(Online Merges with Offline)」の領域で、よく事例として上がってくるのが「スターバックス_モバイルオーダー&ペイ」「ユニクロ_オーダー&ピック」「カインズ_カインズホームアプリ」などです。この3つだけでも、業態も違えば利益構造も違います。自社に近しいビジネスモデルや利益構造の成功事例を参考にしなければ、自社の利益に還元されないデジタルツールやシステムを作ってしまうことにつながります。
ただし、生活者目線で考えると、「購買体験の当たり前」の変化が起きている中で、各社がどのような動きをするか、どのように嗜好性や利便性のあり方が変わっていくのかはウォッチしておくことが重要です。新たなツールやテクノロジーをまずは自分が積極的に使いながら、いまの生活者目線を感じ取ることが求められます。
3.ターゲット(お客様)の違い
さらに、近しい業界/業種の事例においても、各社のターゲットや利用シーンに微妙なズレがあるため、そのまま転用することは危険です。
たとえば、OMO領域で商業施設の活用事例を見てみましょう。国内の商業施設での事例でいえば、パルコが提案する「ポケットパルコ」というものがあります。商業施設パルコを歩くとコインが貯まり、お買い物に使えるポイントに交換できるなど、国内の商業施設ではかなり進んだ提案をお客様に行っています。
しかし、これを電鉄系の商業施設や百貨店が転用したらどうなるでしょうか?商業施設(館)としてのパルコは、駅からやや離れた場所にあるため、「わざわざ足を運んでもらって、いかに自分たちの館に滞在してもらうか?」という前提で機能設計や顧客体験を提案しています。
これを駅近に館を持つ電鉄系の商業施設や百貨店が模倣してしまうと、お客様の求めていることとズレた提案になってしまうのです。駅近の場合、滞在時間ではなく1回5分でも良いのでいかに来館してもらうかの来店頻度を重視すべきなど、そもそも追うべき指標が異なります。
自社のお客様の特性やニーズと照らし合わせながら、本当にハマる事例なのかを見極めることが大切です。筆者自身、多くの事業者様とお話をする中で、この点に悩まれている方が非常に多いという印象を受けています。担当者の方々には、自社のビジネスに対する深い理解と、顧客視点を持つことが求められるのです。
ベンダー選定のポイント
自社のビジネスやKPIを理解し、適切なツールやシステムを提案できるベンダーを選ぶことが重要です。ここでは、ベンダー選定の際に押さえておくべきポイントについて解説します。
- 自社のビジネスとKPIの理解
- ベンダーの提案力と実行力
- ベンダーとのパートナーシップ
- 自社の体制とリソース
筆者は、これまで多くの企業のDXプロジェクトに携わる中で、ベンダー選定に悩む担当者の方々と向き合ってきました。適切なベンダーを選ぶことは簡単ではありませんが、自社のビジネスを深く理解し、ベンダーとの対話を重ねることで、最適な選択ができると確信しています。
みなさんには、この記事で紹介するポイントを参考に、自社に合ったベンダー選定を行っていただきたいと思います。
1.自社のビジネスとKPIの理解
まずは、自社のビジネスとKPIを深く理解することから始めます。どのような商品やサービスを提供し、どのような顧客層をターゲットにしているのか。そして、売上や利益、顧客満足度など、どのようなKPIを重視しているのかを明確にしておく必要があります。
自社のビジネスとKPIを理解することで、デジタルツールやシステムに何を求めているのかが見えてきます。たとえば、ECサイトを運営する企業の場合、サイトのユーザビリティや決済の利便性、商品の検索性などが重要になります。一方、店舗型のビジネスの場合、来店頻度や滞在時間、客単価などを上げるためのツールやシステムが求められます。
2.ベンダーの提案力と実行力
次に、ベンダーの提案力と実行力を見極めることが重要です。自社のビジネスとKPIを理解した上で、適切なツールやシステムを提案できるベンダーを選ぶ必要があります。
ベンダーの提案力を評価する際は、自社の課題やニーズに合わせたソリューションを提示できているかがポイントです。単に最新のテクノロジーを並べ立てるだけではなく、自社のビジネスにどう活かせるのかを具体的に示してくれるベンダーを選びましょう。
また、ベンダーの実行力も重要な評価軸です。提案したソリューションを実際に開発・導入し、運用していく能力があるかを見極める必要があります。ベンダーの過去の実績や、技術者の質、開発プロセスなどを総合的に判断しましょう。
3.ベンダーとのパートナーシップ
ベンダー選定では、単にツールやシステムを購入するだけでなく、長期的なパートナーシップを築けるかどうかも重要な視点です。
デジタル領域は常に変化し続けているため、一度導入したツールやシステムも、継続的にアップデートや改善を行っていく必要があります。そのため、ベンダーとの信頼関係や、コミュニケーションの質も重要な評価軸になります。
課題やニーズを共有し、一緒に解決策を探っていける関係性を築けるベンダーを選ぶことが、プロジェクトの成功につながります。
4.自社の体制とリソース
最後に、自社の体制とリソースも考慮する必要があります。どれだけ優れたツールやシステムを導入しても、自社側で運用やマネジメントができなければ、十分な効果を発揮することができません。
ベンダー選定の際は、自社のIT人材やリソースを把握し、導入後の運用体制を見据えておく必要があります。必要に応じて、ベンダーに運用支援を求めることも検討しましょう。
プロジェクト推進のコツ
プロジェクト推進においては、選定したベンダーとの密なコミュニケーションを図り、プロジェクトの各フェーズにおける目的や期待値を共有することが重要です。ここでは、プロジェクト推進のコツについて詳しく解説します。
- 密なコミュニケーション
- 目的や期待値の共有
- 本質的なニーズの見極め
- 柔軟な対応力
- プロジェクトマネジメントの重要性
- 継続的な改善とフィードバック
筆者自身、多くのDXプロジェクトに携わる中で、プロジェクト推進の難しさを痛感してきました。ベンダーとの協業を成功に導くためには、密なコミュニケーションと柔軟な対応力、そして適切なマネジメントが不可欠です。
担当者の方々には、この記事で紹介したコツを参考に、プロジェクトを推進していただきたいと思います。困難な局面もあるかもしれませんが、ベンダーとの信頼関係を築き、一緒に乗り越えていくことが重要です。みなさんのプロジェクトが成功することを心から願っています。
1.密なコミュニケーション
プロジェクトを成功に導くには、ベンダーとの密なコミュニケーションが欠かせません。単に仕様書を渡して開発を依頼するだけでなく、定期的な進捗報告会や、課題の共有、アイデアの討議などを行うことが重要です。
特に、プロジェクトの初期段階では、自社の要件やニーズをベンダーに正確に伝えることが求められます。ベンダーの提案内容を吟味し、自社のビジネスとの整合性を確認しながら、すり合わせを行っていく必要があります。
2.目的や期待値の共有
プロジェクトの各フェーズにおいて、目的や期待値を明確に共有することも重要なポイントです。
開発段階では、実装すべき機能や性能、スケジュールなどを明確にし、ベンダーと合意形成を図ります。また、テスト段階では、品質の評価基準を設定し、ベンダーと一緒に確認作業を行います。リリース後は、運用面での課題や改善点を共有し、継続的な最適化を図ることが求められます。
3.本質的なニーズの見極め
プロジェクトを進める中で、自社の顧客ニーズと乖離しないよう注意する必要があります。
華美な機能や最新のテクノロジーに惹かれるあまり、本質的なニーズを見失ってはなりません。常に自社の顧客ニーズや、ビジネス課題に立ち返り、本当に必要な機能やサービスは何かを見極めることが重要です。
ときにはベンダーの提案内容に疑問を呈し、自社の方向性を主張することも必要でしょう。
4.柔軟な対応力
デジタル領域のプロジェクトでは、状況の変化に柔軟に対応することが求められます。
技術の進歩や、競合他社の動向、顧客ニーズの変化など、プロジェクトを取り巻く環境は常に変化し続けています。そのため、計画通りにプロジェクトを進めるだけでなく、状況に応じて方向性を変更する柔軟性も必要です。
ベンダーとの密なコミュニケーションを通じて、変化に素早く対応していくことが求められます。
5.プロジェクトマネジメントの重要性
プロジェクトを成功に導くには、適切なプロジェクトマネジメントが欠かせません。スケジュール管理、リソース管理、リスク管理など、プロジェクトの各局面で的確な判断と行動が求められます。
特に、複数のベンダーが関わる大規模なプロジェクトでは、全体の進捗を把握し、各ベンダー間の調整を行うことが重要です。コミュニケーションのハブとなり、プロジェクトの目的や方向性を常に意識しながら、マネジメントを行う必要があります。
6.継続的な改善とフィードバック
プロジェクトの完了後も、継続的な改善とフィードバックを行うことが重要です。リリース後の運用状況をモニタリングし、ユーザーの声を収集することで、改善点や追加の要件を明確化していきます。
ベンダーとも定期的に情報共有を行い、システムの最適化や機能拡張を検討していくことが求められます。デジタル領域は常に進化し続けているため、継続的な改善活動なくして、競争力を維持することはできません。
デジタルベンダーマネジメントに必要なこと
デジタル時代において、ベンダーマネジメントの重要性は高まる一方です。自社の強みを生かしながら、ベンダーの知見やリソースを活用することで、競争優位性を確立することができます。
しかし、ベンダーとの協業を成功に導くためには、適切なマネジメントが不可欠です。最後に、デジタルベンダーマネジメントに必要なポイントを2つ解説します。
- 戦略的なパートナーシップの構築
- ベンダーマネジメントのスキル向上
筆者は、これまで多くの企業のDXプロジェクトに携わる中で、ベンダーマネジメントの重要性を強く感じてきました。デジタル領域では、自社だけでは対応しきれない課題も多く、ベンダーとの協業が不可欠です。しかし、その協業を成功に導くには、適切なマネジメントが求められるのです。
ベンダーとの関係性を、単なる発注者と受注者ではなく、戦略的なパートナーとして捉えること。そして、適切な契約と評価制度を設計し、自社のベンダーマネジメントのスキルを高めていくこと。これらは、どれも容易なことではありませんが、デジタル時代を勝ち抜くために不可欠な取り組みだといえるでしょう。
1.戦略的なパートナーシップの構築
デジタルベンダーとの関係性は、単なる発注者と受注者の関係ではなく、戦略的なパートナーシップとして捉える必要があります。自社の中長期的なビジョンや戦略を共有し、ベンダーと一体となって価値創造を図ることが重要です。
そのためには、ベンダーの選定段階から、自社のビジネスへの理解度や、共創への意欲を重視することが求められます。単に技術力や価格だけでなく、パートナーシップを築ける相手かどうかを見極める必要があります。
2.ベンダーマネジメントのスキル向上
デジタルベンダーとの協業を成功に導くには、自社のベンダーマネジメントのスキルを高める必要があります。単に技術的な知識だけでなく、プロジェクトマネジメントや、コミュニケーション、ネゴシエーションなどのスキルが求められます。
社内でのスキル研修や、外部のセミナー等を活用し、ベンダーマネジメントの知見を高めていくことが重要です。また、プロジェクトの振り返りを定期的に行い、成功要因や失敗要因を分析することで、マネジメントの質を高めていくことができます。
まとめ
デジタル時代において、ベンダーとの協業は不可欠です。その成否を分けるのは、適切なベンダーマネジメントにあります。他社の成功事例に惑わされることなく、自社のビジネスとの適合性を見極め、ベンダー選定を行うことが重要です。
また、ベンダーとの密なコミュニケーションを図り、プロジェクトの目的や期待値を共有しながら、本質的なニーズを見極めていく必要があります。プロジェクトマネジメントの質を高め、柔軟な対応力を持つことで、プロジェクトの成功確率を高めることができるでしょう。
さらに、ベンダーとの関係性を戦略的なパートナーシップとして捉え、Win-Winの関係を構築していくことが求められます。自社のベンダーマネジメントのスキルを高め、適切な契約と評価制度を設計することで、ベンダーとの協業の価値を最大化することができます。
デジタルの波は留まることを知りません。自社の強みを生かしながら、ベンダーの力を活用し、時代の変化に対応していくことが、これからのビジネスの鍵を握っているのです。
この記事を通じて、事例の取り扱い方と、注意するポイントを理解していただけたら幸いです。一緒にデジタルをうまく使いこなし、新たな価値を創造していきましょう。みなさんのご健闘を心よりお祈りしています。