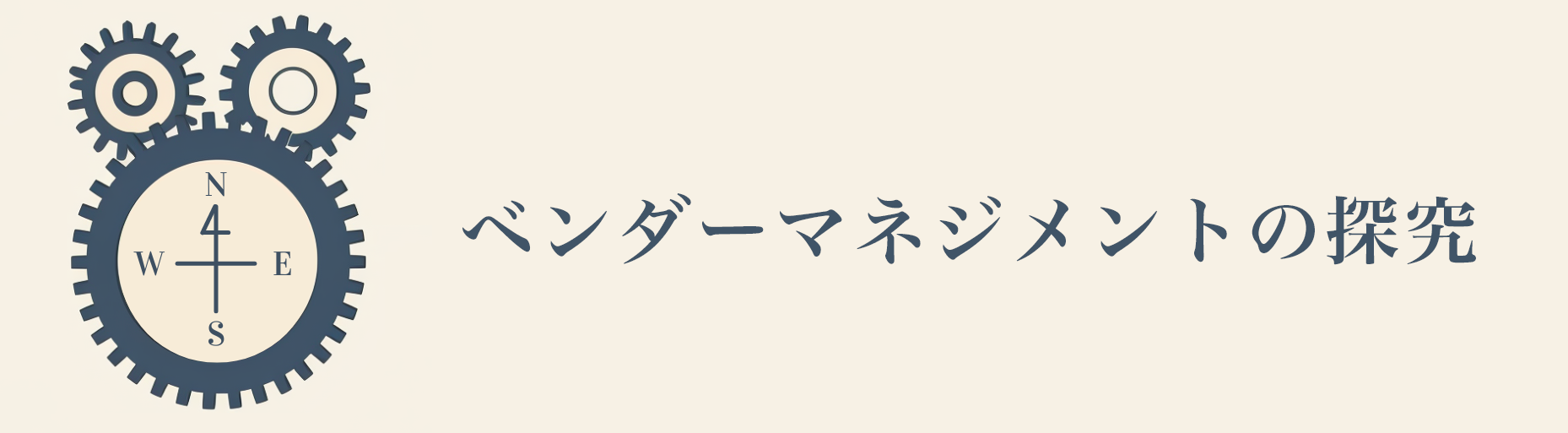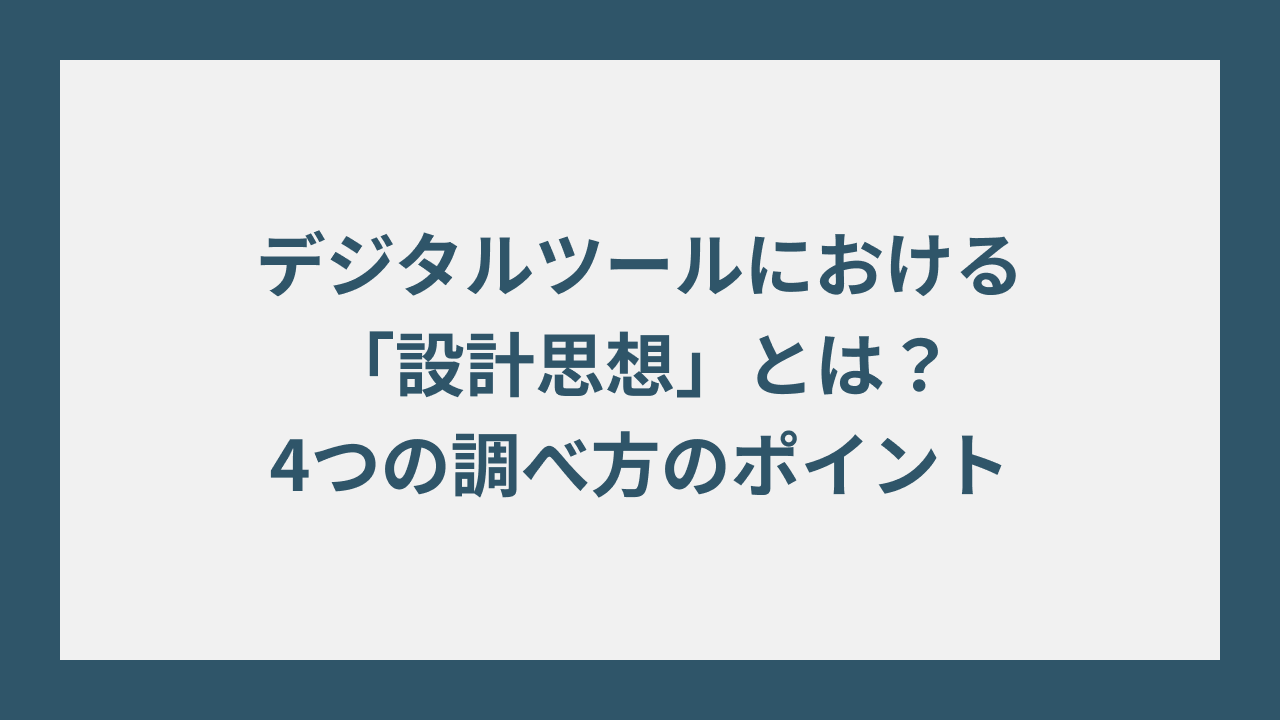デジタル領域におけるプロジェクトを成功に導くには、さまざまな要因が関係しますが、その中でも意外と見落とされがちな「ツールの設計思想」について解説します。知っているだけで役に立つことやツール選定の一つの視点として役に立つことも多いため、ぜひご確認ください。
「設計思想」とは何か
設計思想とは、一般的に図面や仕様書に表現しきれない設計に対するアイデアやコンセプトを指します。図面だけでは伝わりにくい部分を補完する重要な要素ともいえます。
「設計」と聞くと、建築物(家など)を想起する方もいるかと思いますが、デジタルにおいても同じことがいえるのではないかと自分は考えています。「どんな目的や意思(思想)を持って作られたツール(設計物)なのか」を知ることで、ツールの解像度がグッと高まります。
デジタル領域における「設計思想」とは、ツールやサービスが生み出された背景にある考え方や目的のことを指します。それは、開発者や提供者が、そのツールやサービスをどのような目的で作り、どのような課題を解決しようとしているのかを表しています。この設計思想は、ツールやサービスの機能や価格設定、ユーザーインターフェースなどに反映されるもので、それらの原点ともいえます。
「設計思想」を理解することの重要性
ツールやサービスの設計思想を理解することは、そのツールやサービスを効果的に活用し、自社の目的達成につなげるために不可欠です。設計思想の理解が重要である主な理由は次のとおりです。
- ツールやサービスの本質的な価値を見極められるから
- 自社の目的に合ったツールやサービスを選定できるから
- ツールやサービスを適切に使いこなせるから
- ベンダーとのコミュニケーションが円滑になるから
1. ツールやサービスの本質的な価値を見極められるから
設計思想を理解することで、ツールやサービスが提供する本質的な価値を見極められます。機能や価格だけでなく、そのツールやサービスが目指す方向性や解決しようとしている課題を知ることで、自社の目的に合っているかを判断できます。
2. 自社の目的に合ったツールやサービスを選定できるから
設計思想を自社の目的と照らし合わせることで、適切なツールやサービスを選定できます。自社の目的と設計思想がマッチしていれば、そのツールやサービスを活用することで、効率的に目的を達成できるでしょう。
3. ツールやサービスを適切に使いこなせるから
設計思想を理解することで、そのツールやサービスがどのような使い方を想定しているのかがわかります。想定された使い方に沿って活用することで、ツールやサービスの持つ力を最大限に引き出せます。
4. ベンダーとのコミュニケーションが円滑になるから
設計思想を理解することで、ベンダーとの意思疎通がスムーズになります。お互いの目的や価値観を共有できるため、より良い関係性を築ける可能性が高まります。
設計思想の違いによる影響の具体例
ここで、設計思想の違いによる影響を、ASP(Application Service Provider)カートを例に解説します。
ASPカートは、ネットショップを開設するための機能を提供するサービスですが、各社の設計思想には違いがあります。Web上で簡単に調べただけでも、現在私たちが利用できるASPカートは30以上にものぼります。ここでは「BASE」「MakeShop」「Shopify」の3つを例に比較してみます。
BASE
「BASE」は、社内全体の共通言語として「お母さんも使える」という思想があります。今までECをやったことがない方、やってみたいけれど既存のサービスは難しくてわからない方向けにサービスを開発しています。
そのため、BASEはUI/UXがかなりシンプルになっており、初期費用・月額費用0円でECサイトを制作することができます。デザインのカスタマイズ性や機能拡張性が落ちることを許容しているのだと考えられます。「スモールスタートでとにかく始めたい」という方にはおすすめのASPカートだといえます。
MakeShop
一方、GMO社が提供する「MakeShop」は、2004年のサービス開始から時代に合わせて「店舗運営者」のために機能をアップデートしていき、「日本の商習慣に最適化を図ること」を設計思想に置いています。痒いところに手が届く一方で、悪くいえば「まずはシンプルにはじめたい、とにかく試したい」というニーズにはマッチしづらい部分もあります。
Shopify
コロナ禍に日本でもかなり人気になった外資系ASPカートの「Shopify」は、「自分たちの良いと思う仕組みをこちらで用意するので、事業者がそれに合わせてビジネスを展開して欲しい」という設計思想となっています(Shopifyに限らず外資系ツールに多い傾向です)。そのため、日本製のツールのように「カスタマイズありき」の発想とは真逆だといえるでしょう。
また、多くの外資系サービスには、日本のITベンダーにはある「営業チーム」がそもそもなく、問い合わせしても返ってこないことも多々あります。その代わりに、「パートナー」や「エヴァンジェリスト」制度を設け彼らを支援し、営業や説明なども彼らが行うことを促しています。
3つのASPカートの比較
3つのASPカートを例に比較してみました。ツールを開発する時点の設計思想が異なると、一口に「ASPカート」といっても大きく違う提供価値になることがおわかりいただけたでしょう。
筆者は前職がShopifyに強い会社に勤めていたため、ShopifyでのEC開発のオーダーを聞くことが多くありました。商談の中で、そもそもECサイトをはじめとしてデジタル領域での知見がないチームで、運営体制も強化しにくいといった事情がある事業者様には、Shopifyの設計思想から各種機能などについて説明させてもらい、BASEやMakeShopをテーブルに上げながら議論をさせてもらうことも多くありました。この説明をさせてもらう際に、「設計思想」から説明をすると理解が進みやすく、お互いにより良いコミュニケーションができた経験があります。
「自分たちが導入するツールやサービスでどんなことを達成したいのか?」と自分たちの目的を整理することはみなさんよく実施すると思いますが、「検討するツールやサービスはどんなことを達成するために生まれたのか?」といった設計思想もチェックしておくと、より良いプロジェクトにすることができます。
自社の目的に合ったツールを選ぶために重要なこと
ツールやサービスの設計思想を理解することは、自社の目的達成に適したツールやサービスを選定するために非常に重要です。自社の導入目的と設計思想がずれていると、期待した効果が得られなかったり、かえって非効率になったりすることがあるからです。
たとえば、高機能なASPカートを選んでしまうと、操作方法の習得に時間がかかり、本業に集中できなくなる可能性があります。逆に、大規模なネットショップ運営には、必要十分な機能を備えたASPカートを選ぶ必要があります。
自社の目的と設計思想とのマッチングを考えることで、最適なツールやサービス選定につながります。そのためには、自社の現状と目指す方向性を整理し、優先順位をつけることが大切です。
「設計思想」の調べ方のポイント
ツールやサービスの設計思想を調べるにあたっては、重要なポイントがあります。ここでは、主なポイントを7つに分けて解説します。
- 運営会社の背景を調べる
- 提供開始時期と対象ユーザーを確認する
- 代表者やキーパーソンのインタビューを読む
- 導入事例は参考程度にする
- 実際に使ってみる
- 競合サービスと比較する
このように、運営会社の背景、提供開始時期、対象ユーザー、キーパーソンのインタビュー、導入事例、実際の使用感、競合サービスとの比較など、多角的にアプローチすることで、ツールやサービスの設計思想を深く理解することができます。
1. 運営会社の背景を調べる
設計思想を理解するには、運営会社の背景を知ることが大切です。会社の設立経緯や事業展開、抱えている課題などを調べることで、そのツールやサービスが生まれた理由、設計されたのか目的などを推測できます。
具体的には、会社のホームページやニュースリリース、会社案内などを確認しましょう。また、会社の採用情報を見ることで、どのような人材を求めているのかがわかり、会社の方向性を知る手がかりになります。
2. 提供開始時期と対象ユーザーを確認する
ツールやサービスの提供開始時期を知ることで、その時代の技術的な背景や、社会的なニーズを読み取ることができます。たとえば、スマートフォンの普及期に提供が開始されたツールであれば、モバイル対応を重視した設計思想であることが推測できます。
また、対象ユーザーを確認することも重要です。個人向けなのか、企業向けなのか、あるいは特定の業種や職種に特化したツールなのかを知ることで、設計思想がどのようなニーズに応えようとしているのかを理解できます。
3. 代表者やキーパーソンのインタビューを読む
ツールやサービスの設計思想を直接知るには、代表者やキーパーソンのインタビュー記事を読むことが効果的です。開発の背景や目指す方向性、将来のビジョンなどを直接確認することができるため、設計思想への理解が深まります。
インタビュー記事は、技術系のメディアやビジネス誌、新聞などに掲載されていることがあります。また、運営会社のブログや社内報などにも、社内の重要人物の考えが記載されていることがあるため、チェックしてみることをおすすめします。
4. 導入事例は参考程度にする
ツールやサービスの導入事例は、設計思想を知るための参考情報として活用しましょう。ただし、導入企業の事情は千差万別であるため、鵜呑みにせず、あくまで参考程度に留めることが大切です。
導入事例を見ることで、そのツールやサービスがどのような課題解決に役立っているのか、どのような業種や規模の企業に導入されているのかがわかります。設計思想との関連性を考えながら、自社の目的達成に役立ちそうな事例を探してみてください。
5. 実際に使ってみる
設計思想を肌で感じるには、実際にツールやサービスを使ってみることが一番です。
多くのツールやサービスでは、無料トライアルや機能制限付きのフリープランが用意されています。これらを活用して、操作性や機能の充実度、ユーザーサポートの質などを確かめてみましょう。
使用感は設計思想の表れでもあります。インターフェースがシンプルで直感的に使えるツールは、ユーザーの利便性を重視した設計思想だといえます。一方、多機能で融通の利くツールは、ユーザーのニーズに柔軟に応えようとする設計思想の表れだと考えられます。
6. 競合サービスと比較する
競合サービスと比較することで、そのツールやサービスの設計思想の特徴が浮き彫りになります。
同じ目的を持つツールでも、力を入れているポイントは異なるはずです。たとえば、あるツールが高機能である一方、別のツールはシンプルで使いやすいといった具合です。それぞれの特徴を比較することで、設計思想の違いを明確に理解できます。
設計思想を理解することがプロジェクト成功につながる
IT・デジタル領域でのプロジェクト成功のカギを握るのは、ツールやサービスの設計思想への理解と、それを自社の目的達成に活かすことです。設計思想を知ることは、次のような効果を期待できます。
- ツールやサービス選定の精度が上がり、無駄な投資を防げる
- ツールやサービスの適切な活用方法がわかり、業務の効率化が図れる
- ベンダーとの良好な関係が築け、円滑なプロジェクト運営が可能になる
設計思想の理解は、優れたツールやサービスを見極め、それを自社の力にしていくために欠かせません。
IT・デジタル領域に携わるみなさまには、ツールやサービス選定の際に、設計思想を知ることを習慣づけていただきたいと思います。機能や価格だけでなく、設計思想にも目を向けることで、プロジェクトの成功に大きく近づくことができるはずです。
設計思想を読み解く力は、自社に最適なツールやサービスを選ぶために欠かせないスキルです。今回解説したポイントを押さえて、設計思想への理解を深めていきましょう。プロジェクトの成功に導く、重要な一歩となるはずです。