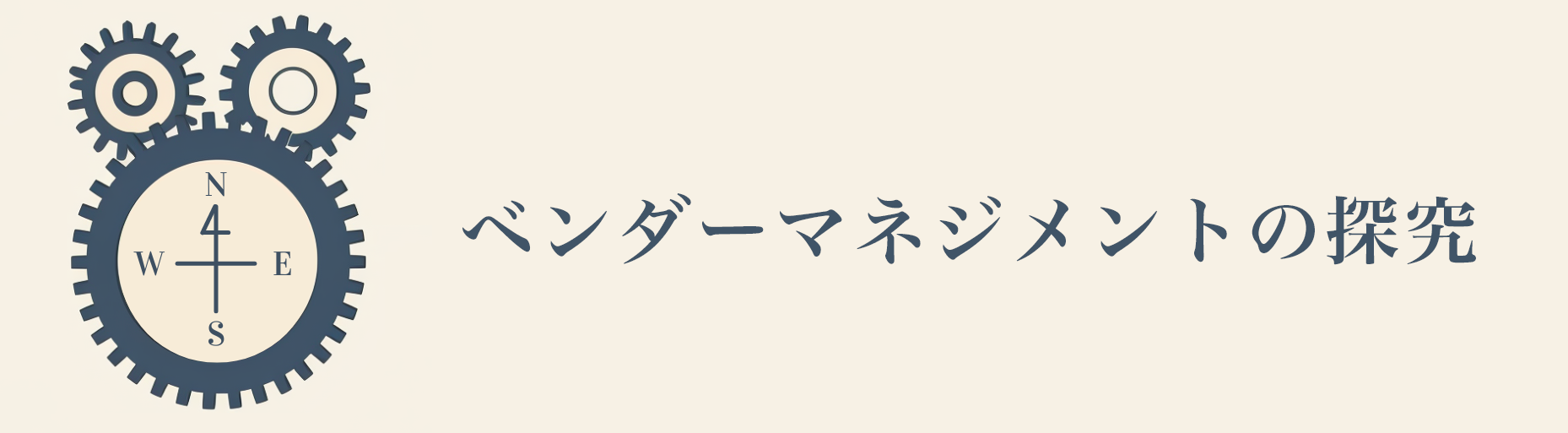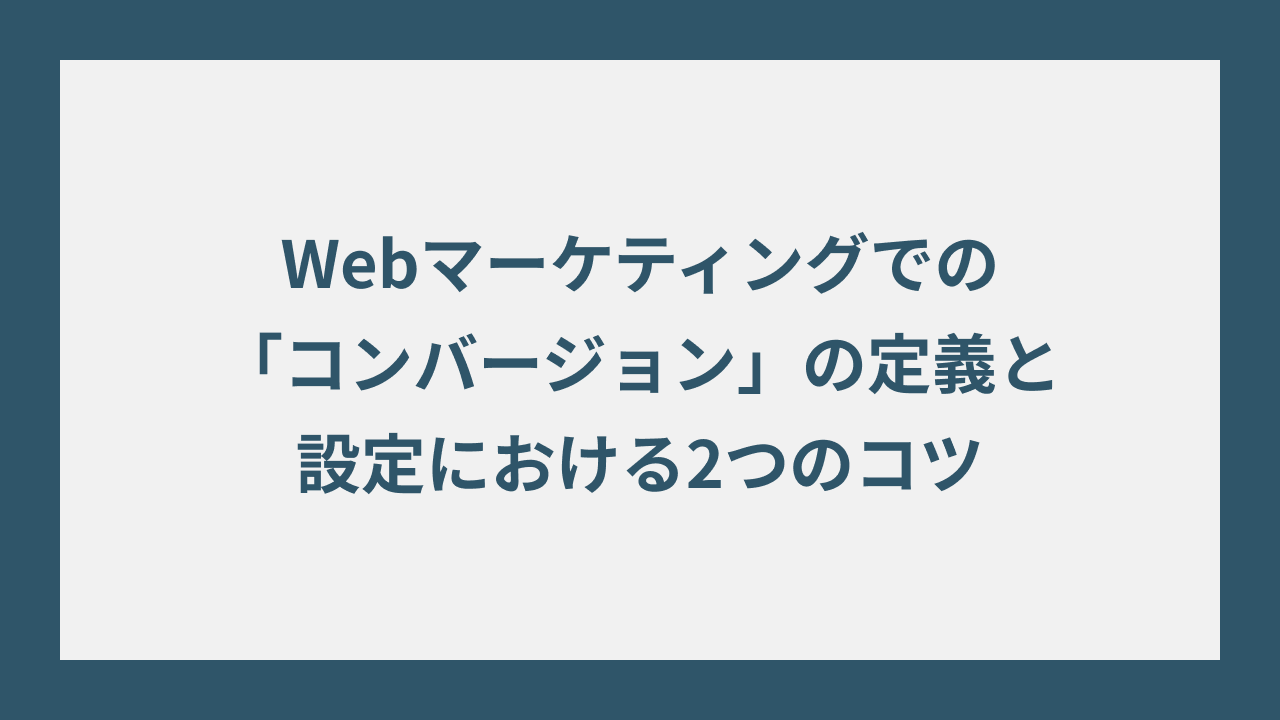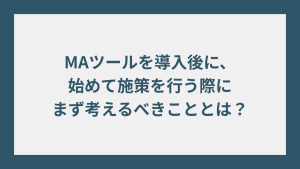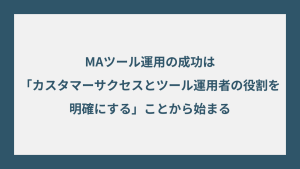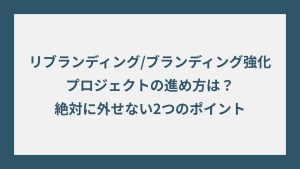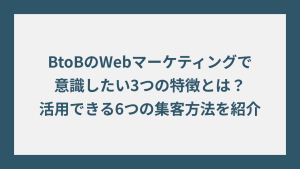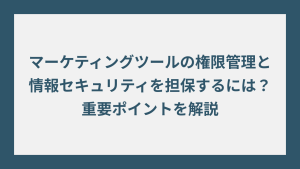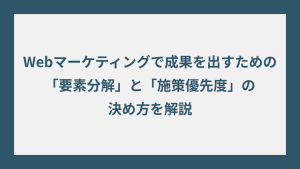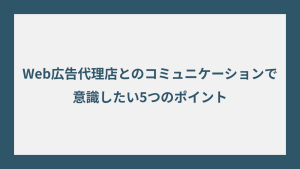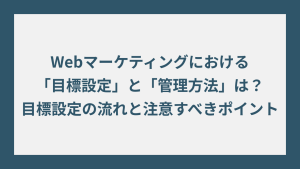この記事では、事業にWebマーケティングを活用する上で切っても切り離せないコンバージョンの定義と、それを事業やサービスごとにどのように設定するのが良いのかについて具体例を挙げながら解説します。
Webマーケティングにおけるコンバージョンとは
コンバージョン(CV)とは、Webサービスに訪れた人が行った特定の行動を指します。「特定の行動」なので、定義は事業やサービスによって本当にさまざまです。あくまでも一例ですが、次のような行動がコンバージョンとして定義されます。
- 購入完了
- サブスクリプション登録
- フォーム申し込み完了
- 電話問い合わせ
- メールマガジン登録
- 会員登録
- 資料請求ダウンロード
- コメント、口コミ投稿
- フォームボタンのクリック
- 電話番号ボタンのクリック
- SNSアカウントのフォロー(友だち追加、チャンネル登録など)
- SNSでのシェア、投稿
- 動画コンテンツの閲覧
- 詳細コンテンツの閲覧
- 関連サイト、ページへの遷移 など
Webマーケティングにおいては、計測しようと思えばユーザーのWeb上でのさまざまな行動を計測することができます(と言いつつ、Webで計測できないところでどんな思考や行動、判断をしているか想像することも大変重要なのでお忘れなく)。
事業やサービスにWebマーケティングを活用する場合は、その成果に直接的に、もしくは間接的につながり得るユーザーの行動をしっかりと計測することが重要です。ただし、闇雲にすべての行動を細かく追いすぎても仕方ないため、事業やサービスにとって直接的に成果につながる主要なコンバージョンと、間接的に成果に繋がり得るコンバージョン(マイクロコンバージョンと表現されることが多い)とをそれぞれ定義し、チーム内でも認識を揃えた上で定点観測することをおすすめします。
コンバージョンの定義を揃える
上記の通り、一つの事業でもさまざまなコンバージョンの定義が存在し得るため、自社内チームはもちろん、各種協力会社(Web広告代理店や制作会社、MAツールベンダーなど)も含めて定義を揃えて、円滑にコミュニケーションが取れる状態をまずは整えましょう。この定義がズレたままだと、改善のための施策が明後日の方向に行ったり、見かけ上のレポートと実績が大幅に乖離していたりといったことが起こりかねません。
コンバージョン設定のコツ①:ハードルを意図的に調整する
みなさんも普段からWebサイトやアプリに触れる機会があると思います。その際、初めて訪れたサイトや初めて利用したアプリを、まるで幼馴染の親友のように、最初から信頼するでしょうか?きっと多くの方がそんなことはないと思います。むしろ、最初はかなり警戒しながら扱うのではないでしょうか?また、多くの事業やサービスには必ずといっていいほど、競合となる事業やサービスが存在するはずです。
初めてWebサイトに訪れた人にしっかり信頼されるような情報提供(価値提供や期待感の創出なども含む)やコミュニケーション設計ができているか、競合サービスに勝る魅力が打ち出せているかは、大前提ではありますが非常に重要な要素です。
そして、その上でコンバージョンのハードルを意図的に調整することが重要です(無闇にコンバージョンのハードルを下げることはまったくおすすめしません。事業やサービスにとって重要でない顧客を評価してしまったり、コンバージョンした後の工程においてリソースの無駄遣いが起こってしまったりする可能性が高いからです)。
たとえば、コンバージョンのハードルを調整する一例として、月額10,000円の化粧品をリピート通販の形で販売している事業について考えてみます。新規の顧客にいきなり月額10,000円の化粧品購入をしてもらうことはハードルが高いので、まずは無料お試し(もしくは少額購入)という形で入口としてのコンバージョンのハードルを下げ、満足してもらった方に対して定期購入のアプローチを取る方法などがあります。
事業やサービスによってさまざまですが、自分たちの事業やビジネスモデルの場合どういったコンバージョンのハードル設定ができるか、上手くいっているもの(他分野も含む)を参考にしつつ、金額や期間、利便性などの軸で検証していくと良いでしょう。
コンバージョン設定のコツ②:情報を付加する
成果把握の解像度を上げるために、コンバージョンに「重み付け」したり、「切り口」を付加したりすることが非常に重要です。こうしたデータをもとに分析をすることで、初めて具体的な課題点を発見し、改善するための打ち手につなげることができます。
では、具体例を踏まえて解説します。
コンバージョンに重み付けをして成果改善につながった事例
あるECサイトを運営しているA社では、「コンバージョン=ECサイトでの購入完了」と定義していました。ECサイトでの購入数は年々伸びているものの、売上や利益額が伸び悩んでいることが経営課題となっていました。
ECサイトへの流入獲得はWeb広告をメインに活用していましたが、広告媒体側では売上を計測しておらず、とにかく購入数が多く獲得できる広告媒体に予算を寄せていました。そのため、まずは広告媒体側で売上計測できるようにコンバージョンである購入完了ごとに「購入金額」も併せて計測するように設定し、購入完了ごとの「購入単価」を可視化しました。
そのデータをもとにWeb広告の媒体別の成果を検証したところ、予算を大きく投資していた広告媒体の「購入単価」が実は他媒体よりも明らかに低かったことが判明しました。
そこで、「購入単価」をもとにした予算の再分配を行いました。結果的に、見かけ上のコンバージョン単価(1コンバージョンを獲得するために投資した金額)は高くなったものの、ECサイトの売上と利益額は大きく伸長しました。
コンバージョンに切り口を付加して成果改善につながった事例
MAツールを提供しているB社では、「コンバージョン=Webサイトでのお試し申し込み完了」と定義していました。
B社のMAツールは法人向けのサービス(月額課金モデル)で、お試し申し込み後は必ずインバウンドの営業担当が状況のヒアリングやMAツール利用のオンボーディング(使い方や活用方法の初期レクチャーなどを指す)を行っていました。ここ数年、お試し申し込みしてくれる会社数自体は増えているものの、その後の有料化率がなかなか上がらずに売上も横ばいの状態が続いていました。
過去実績のヒアリングとデータ分析を実施したところ、お試し期間中にMAツールを利用したことで成果が出ている会社の有料化率が著しく高いことが確認できました。そのため、有料化率を改善するための打ち手として、「Webサイトでのお試し申し込み完了」の際に、「想定されるツールの活用方法」や「利用人数」、「期待すること」などの情報を追加で取得しました。そして、申込順にすべてのすべての申込に対応していくのではなく、特定の切り口で振り分け、B社のMAツールを利用することで短期的に成果を出しやすい状態の会社を優先して注力的にオンボーディングすることで、全体としての有料化率が大幅に改善しました。
成果改善につながった事例からわかること
こうした事例を通じてお伝えしたいことは、みなさんの事業やサービスにとって、本当の顧客は誰なのか、そして誰を大事にすべきなのかを明確にすることの重要性です。
当たり前ですが、リソース(時間、お金、人)は常に有限です。Webマーケティングにおけるコンバージョンは非常に使い勝手の良い概念ですが、こうして「重み付け」したり、「切り口」を付加したりすることで初めて実際の現場での活用に耐えるものだと考えています。
まとめ
Webマーケティングにおけるコンバージョンの定義と設定のコツについて、具体的な事例も交えながら解説しました。事業の維持・拡大に最大限Webマーケティングを活用するための一助となれば幸いです。
私たち株式会社Geneは、デジタルベンダーマネジメントという領域に強みをもち、総合的な観点から事業会社のよりよいベンダー選定や事業推進の一助となれるよう、これまで数多くの現場で尽力してきました。Webマーケティングにおけるコンバージョンの定義や設定の仕方にお困りの方がいらっしゃいましたら、ぜひお気軽にご相談ください。