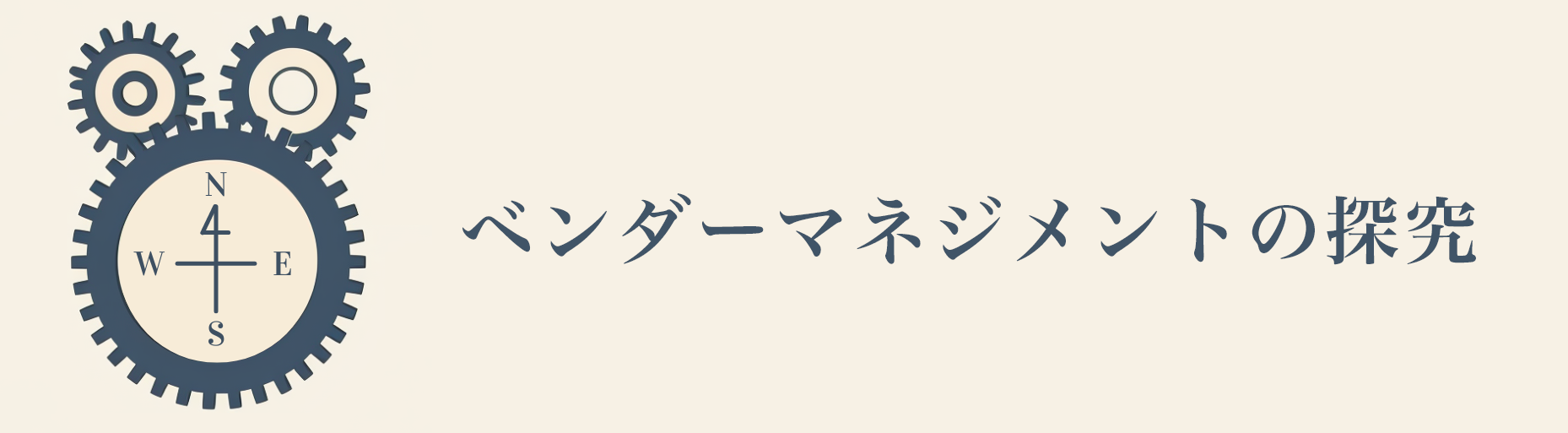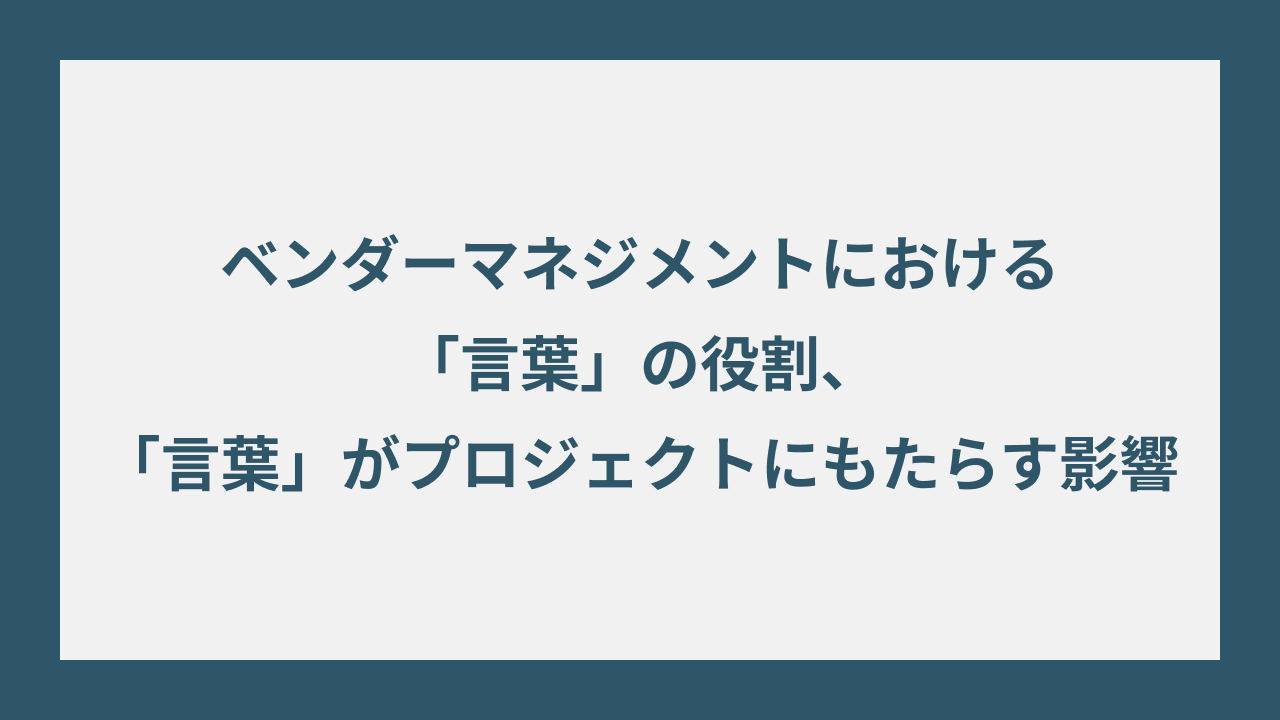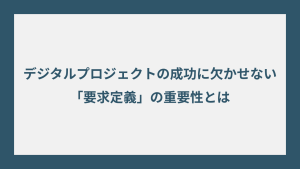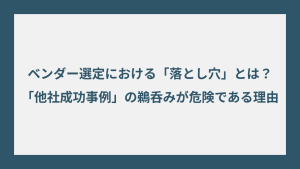プロジェクトの大小の規模に関わらず、複数人でプロジェクトを行う際は、プロジェクトの中心に「言葉」が存在していると考えています。この「言葉」とはコンセプチュアルでキャッチーな言葉のみではなく、たとえば「プロジェクトの目的=〇〇」などを示すものも含んでいます。
筆者は、マーケティング/PRの統合プランニングやブランディング領域でコピーライターやプランナーをしていた経験があり、複数のベンダーさん(主に広告代理店さん、PR会社さん、制作会社さん、ITベンダーさん)を横断して行うプロジェクトにおける言葉の効用と弊害を多く経験してきました。
プロジェクトにおける「言葉」とはコピーライターがつくるものでもありませんし、マーケティング/PR領域にとどまるものでもないと考えています。本記事では、ベンダーマネジメントを行う中で、「言葉」をいかに道具として使っていくのか、現段階での最適解について解説します。
言葉の大切さを主張する記事では、どうしても「コピーライティング」や「言語化力」という括りにされがちです。また、コピーライティングはどうしてもマーケティング領域(主に広告、プロモーション)に限った話になってしまうため(著者はそうは思いませんが)、本記事内では、広義の言葉が持つ力をあえてそのまま「言葉力」と表現致します。
「言葉」があるおかげで、我々は存在の“定義”をすることができ、“違い”を正しく認識できると考えています。また、仕事における言葉とは、それを通じて他者との関係性を創るものとも考えており、ベンダーマネジメントにおいても一つひとつの「言葉」へのこだわりを持って、価値創造していきたいと思っています。
「言葉力」を身につけることで、「言葉」をプロジェクトの潤滑油や誘い水にすることができ、より良いベンダーマネジメントを行うことが可能です。
本記事では、プロジェクトにおいて、外部ベンダーさんや関係する部署にプロジェクトの目的や意図を説明していく役割を担う方々(主に事業会社、総合代理店など)はどのように言葉を開発/設定していくとよいか、またその目的や意図の説明を受けて具体遂行をする側の方々(制作会社さん、ITベンダーさんなど)はどのように「言葉」を受け取り、最適な価値創造をしていけばよいのかについて書いていきます。
一方で、今回は事業者サイドからの「言葉」の扱い方について書いていきますが、全ての「言葉」は事業者側主導であれば良いという風には考えておりません。ベンダーサイドにはベンダーサイドで、彼らの言語から発せられる「言葉」があり、そこへのリスペクトを持ちながら、適宜翻訳と編集を行なっていくことがより良いプロジェクトを生むことだと考えており、双方にとってより良いコミュニケーションへどうあるべきか?についても別の記事で書いていきたいと思います。
プロジェクトにおける言葉の役割、効用
まずは、「プロジェクトにおける言葉の役割、効用」について解説します。プロジェクトにおける言葉の役割としては、大きく次の3つがあると考えています。
- プロジェクトの焦点を明確にできること
- コミュニケーションの効率化を図れること
- 個人の創造性の促進すること
1. プロジェクトの焦点を明確にできること
主にプロジェクトの目的や重要な要素を簡潔に表現し、プロジェクトメンバーや関係者が一貫した方向性を持ち、目標を達成しやすくするために「言葉」を使います。1.の役割で「言葉」を開発/設定する際、筆者は次のことをクライアントさんと確認することが多いです。
- 口ずさみやすいか、口馴染みがあるか(自分たちで話して違和感/無理がないか)
- その言葉からアクションを考えられるか(逆に思考の制限をしていないか)
2. コミュニケーションの効率化を図れること
そのままの意味で「言葉」を軸にして、コミュニケーションの効率化を狙います。迷ったら立ち戻る場所にしたり、一つの判断基準にしたりもしますが、ベンダーマネジメントにおいて注意が必要なのは、その言葉を適切に翻訳することです。
「言葉」とは本来的には会社組織の歴史や文化から滲み出てくるものです。それにリスペクトを持って使うことはもちろん大切なのですが、さまざまなベンダーさんと連携する際に、その言葉をそのまま使ってしまうと、ベンダーさん側の会社組織の歴史や文化(もしくは業界)から、正しく認識できないことがあります。
たとえば、「コンセプト」「システム」「コンバージョン」「クラウド」などは業界によって認識が変わりやすい言葉です(他にもたくさんありますし、組織によって大きく異なるため、都度すり合わせをするようにしています)。
ベンダーマネジメントのつなぎ手として私がプロジェクトに関わる際には、この言葉の翻訳にはかなり注意を払いながらするようにしています。
3. 個人の創造性の促進すること
1.の自分たちで話して違和感/無理がないかにも通ずる部分ですが、言葉としては綺麗だったり、それらしい表現だったりしても、現場の方々が熱気を持って考えてみようやってみようと本気で思えるものかということも大切にしています。
「過度な単純化」をしてしまうことは、プロジェクトや問題の複雑さが無視されることがあります。必要な情報や複雑さを適切に伝えるということも意識しています。具体的には次のようなことを意識しています。
- キャッチーすぎる、短すぎる言葉は注意(広告コピーであればOKな場合も)
- 横文字は極力使わない(それっぽくなってしまう)
- どこかから引用した言葉で、チームとしての言葉ではない
たとえば、直近のデジタル界隈でのバズワードである「DX」にしても「OMO」にしても、自社にとっての「DX」とは、自社にとっての「OMO」事業を行う現場の皆さんと一緒に考えるべきだと感じています。
「言葉の重要性」を体現している企業の例
国内の企業で言えば、サイバーエージェントさんは藤田社長がかなり言葉へのこだわりを強く持ち、組織としても大切にされている企業だと感じています。以下の参考記事にもありますが、「言葉がチーム力の最大化」には必要と言い切っており、急速な成長や強い組織作りの一助に「言葉」が役に立っていることを感じます。

言葉の開発・設定
最後に、今後ベンダーマネジメントを行っていく方々に、どのように言葉を開発/設定していくかについて現時点で筆者が考えているものを書いていけたらと思います。
前提として、仕事における「言葉」とは、書くものではなく、見つけるものという認識でプロジェクトに臨むようにしています。言葉の役割の明確化、誰に向けての言葉か、表現としてわかりやすいかなどの「言葉を書く力」も大切ですが、それ以上に「聞く力」、そしてそこから「発見する力」を重視しています。
クライアントらしさのある言葉は、現場の皆さんの中や、そのお客さまの中に存在しています。その言葉を“発見”するためには、たくさんの関係者の話を“聞く”こと。
聞くことで手に入った多くの要素から、核となる原石を見つけ、共に磨き上げていく。それが前述にある、「言葉」で存在の“定義”をし、“違い”を正しく認識し、「言葉」を通じて他者との関係性を創ることだと考えています。
そんな言葉がプロジェクトに一つあることで、プロジェクトの成果にも効いてくるはずです。もちろん、時間も労力も必要ですが、より良いベンダーマネジメントのために、確実に一歩ずつ進んでいきましょう。